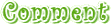豪農の館ーコヤノ美術館西脇館ーの写真ブログ。コヤノ美術館HPへはプロフィールのHPアドレス若しくはリンクよりどうぞ。
カレンダー
プロフィール
HN:
K
HP:
性別:
女性
自己紹介:
コヤノ美術館西脇館~豪農の館~
住所
〒677-0004 兵庫県西脇市市原町139番地(鍛冶屋線
市原駅記念館 隣り)
開館日
毎週土曜・日曜日。午前10時~午後5時(冬季は午後4時まで)
問い合わせ
TEL:(06)6358-4930
(月曜~土曜 午前9時~午後6時まで)
mail:koyano@koyafron.co.jp
住所
〒677-0004 兵庫県西脇市市原町139番地(鍛冶屋線
市原駅記念館 隣り)
開館日
毎週土曜・日曜日。午前10時~午後5時(冬季は午後4時まで)
問い合わせ
TEL:(06)6358-4930
(月曜~土曜 午前9時~午後6時まで)
mail:koyano@koyafron.co.jp
リンク
カテゴリー
ブログ内検索
最新コメント
[01/04 ブロッサム]
[02/09 白い家具]
[08/01 興味津々丸]
[07/28 意匠創作のふたり]
[07/05 おにかま]
最新記事
(09/06)
(05/13)
(04/18)
(03/18)
(01/16)
カウンター
2025.04.03
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2014.02.21
大阪名所欄間
コヤノ美術館西脇寛の明治の主屋の座敷には、大阪の名所をあしらった4つの欄間があります。
中でも目を引くのは、天神橋の欄間です。
鉄橋を欄間にあしらっているというのは珍しく、主屋が文化財に登録された際にも、解説として欄間について触れられています。

こちらがその欄間。
左下にはポンポン船、右上には大阪城の石垣も彫られています。
「天神橋」は江戸時代から「天満橋」、「難波橋」とともに難波三大橋に数えられています。
元は木製の長い橋で、わらべ歌にも「天神橋長いな、落ちたらこわいな」と歌われる程でした。
大阪では民間で資金を出し合って橋を架ける「町橋」の文化があり、明治時代には、輸入した鉄橋が次々にかけられました。
また、1885年(明治18年)の淀川大洪水により多くの橋が流失や被害を受けた事を機に、大阪市内の18の橋が鉄橋などに架け替えられました。
そして、その中でも、人々の注目の的となったのが、1888年(明治21年)に完成した「天神橋」。この欄間に描かれている橋です。
天神橋は、5径間から成り、その最大支間は65mと、道路橋としては当時最大規模で、その大きさに、人々は大変驚いたそうです。
また、当時珍しい、車道と歩道が分離した橋でした。

分りやすいように、欄間の下には明治28年に刷られた天神橋の絵も展示。
しかし、なぜ大阪の名所を?
大阪への憧れだったのか、はたまた大阪からのお客様が多かったのか。
いずれにしても、珍しい欄間です。
中でも目を引くのは、天神橋の欄間です。
鉄橋を欄間にあしらっているというのは珍しく、主屋が文化財に登録された際にも、解説として欄間について触れられています。
こちらがその欄間。
左下にはポンポン船、右上には大阪城の石垣も彫られています。
「天神橋」は江戸時代から「天満橋」、「難波橋」とともに難波三大橋に数えられています。
元は木製の長い橋で、わらべ歌にも「天神橋長いな、落ちたらこわいな」と歌われる程でした。
大阪では民間で資金を出し合って橋を架ける「町橋」の文化があり、明治時代には、輸入した鉄橋が次々にかけられました。
また、1885年(明治18年)の淀川大洪水により多くの橋が流失や被害を受けた事を機に、大阪市内の18の橋が鉄橋などに架け替えられました。
そして、その中でも、人々の注目の的となったのが、1888年(明治21年)に完成した「天神橋」。この欄間に描かれている橋です。
天神橋は、5径間から成り、その最大支間は65mと、道路橋としては当時最大規模で、その大きさに、人々は大変驚いたそうです。
また、当時珍しい、車道と歩道が分離した橋でした。
分りやすいように、欄間の下には明治28年に刷られた天神橋の絵も展示。
しかし、なぜ大阪の名所を?
大阪への憧れだったのか、はたまた大阪からのお客様が多かったのか。
いずれにしても、珍しい欄間です。
PR

 管理画面
管理画面